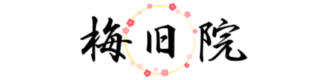1.破産手続について
1.1.破産管財手続とはどのようなものでしょうか。
破産管財手続とは、借金などの債務の支払ができないときに、裁判所の決定を受けて、破産管財人が法人を清算する手続です。
破産者の財産は、梅旧院の代表者ではなく、破産管財人が全て管理し、換価を進めていくことになります。
1.2.債権者集会はいつでしょうか。
債権者集会を開かない非招集型(破産法31条4項)です。
したがいまして、現時点で債権者集会の予定はありません。
1.3.梅旧院は宗教法人として解散になるのでしょうか。
破産手続の開始決定を受けたことにより、梅旧院は自動的に解散となります(宗教法人法43条2項3号)。
もっとも、本院の墓地や分院の納骨堂の引継などを完了し、破産手続が終了するまでは、宗教法人として存続することとなります(宗教法人法48条の2)。
また、破産手続開始決定により、墓地や納骨堂の経営許可(墓地、埋葬等に関する法律10条1項)が失われることはありません。
1.4.裁判所や破産管財人から送付された書類を提供するよう求める第三者がいます。応じる必要はあるでしょうか。
裁判所や破産管財人からお送りした書類について、提供を求める権限を有する者はおりません。
ですので、第三者が提供するよう依頼してきたとしても、これに応じる必要はありません。
2.本院の墓地について
2.1.本院の墓地はどうなるのでしょうか。
墓地を含む本院の土地は、破産申立前に、競売手続により、第三者が取得しています。
現在、土地を競落した第三者(以下「競落人」といいます。)との間で、墓地として残すことができないかを含め、協議を行っています。
2.2.本院の墓地から無断で墓石や遺骨が移動されてしまわないでしょうか。
破産管財人が墓石や遺骨を無断で移動させることはありません。
また、墓地に永代使用権があれば、墓地に設置された墓石を第三者が無断で取り去ることはできません。
遺骨についても、移動には墓埋法(墓地、埋葬等に関する法律)の許可(同法5条)を得ることが必要ですので、第三者が無断で移動させることはできません。
2.3.墓地の競落人から墓石や遺骨の撤去を求められた場合、応じないといけないのでしょうか。
墓石が存在する場合、永代使用権を墓地の競落人に対抗(主張)することができると考えられています。
したがいまして、墓地の競落人やその依頼を受けた業者が一方的に墓石や遺骨の撤去を求めることはできません。
また、競落人からの協議の申出に対して、応答する義務もありません。
応答しないことにより、永代使用権者が不利になることもありません。
なお、墓石の撤去にあたり、遺骨を預かるという業者がいますが、永代使用権者であっても、改葬先を定めて天王寺区役所の許可を得ること(Q2.7)をせずに遺骨を移動させることは、墓埋法5条1項に触れることとなりますので、ご注意ください。
2.3.1.墓地の永代使用権を競落人に主張できるのは、破産手続が続いている間だけでしょうか。
墓地使用権を競落人に主張できるのは、永代使用権を有する方の固有の権利であり、破産手続が続いているかどうかとは無関係です。
破産手続が終了し、破産管財人が任務を終えたとしても、競落人に主張し続けることができます。
なお、墓地の存続についての結論を得るまでに、破産手続を終了させることはありません。
2.3.2.墓地が譲渡されて第三者が墓地の所有者となったとしても、永代使用権を新しい所有者に主張することはできるのでしょうか。
主張することができます。
2.4.現在、梅旧院本院のお墓にお参りできるでしょうか。
住職は不在ですが、梅旧院本院のお墓にお参りいただくことが可能です。
なお、立入禁止の立て看板がありますが、永代使用権者に向けられたものではありません。
遠慮なく墓参ください。
2.5.墓参時に水道を使用することはできるでしょうか。
水道を使用していただいてかまいません。
なお、令和7年2月11日時点で蛇口が破損しておりましたが、2月12日に修理を完了しております。
墓地については定期的に清掃、除草作業、ゴミ処理をしていますが、お気付きの点があれば、contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
2.6.本院の墓地の使用者です。新たに遺骨を納骨することはできるでしょうか。
(1) 納骨の可否
納骨(埋蔵)いただくことが可能です。
(2) 納骨手続書類の準備(埋葬許可証)
納骨には埋葬許可証が必要となりますので、ご準備ください。
多くの場合、骨壺の袋に火葬場の職員が入れてくれています。
お手元にない場合は、埋葬許可証を発行した市役所等で再発行を受ける必要があります。
(3) 法要
納骨のための法要を手配いたしますので、contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、お名前と電話番号を必ず記載してください。
2.7.本院の墓地から他の墓地に改葬することはできるでしょうか。
(1) 改葬の可否
改葬いただくことが可能です。
(2) 改葬手続書類の準備(受入証明書・納骨証明書・改葬許可申請書)
まず、改葬先の墓地等から、受入証明書を取得してください。
受入証明書の提示を受け次第、破産管財人が納骨証明書を発行します。
これらの証明書やその他の必要書類とともに、改葬許可申請書に必要事項を記載し、天王寺区役所に提出してください。
その他の必要書類等は天王寺区役所のウェブサイトでご確認ください。
(3) 墓石の移転
また、墓石の移転を行う業者も併せてご準備ください。
もっとも、破産管財人その他が特定の業者を指定することはなく、任意の業者で結構です。
(4) 法要
本院墓地からの改葬のための法要は、破産管財人が手配いたします。
contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、お名前と電話番号、メールアドレスを必ずご記載ください。
2.8.破産管財人から墓地使用料の請求書が届きました。払わなければならないのでしょうか。
Q2.2.のとおり、永代使用権があれば、第三者に対して墓地の権利を主張することができると考えられます。
しかし、墓地使用料のお支払いがない場合、墓地の使用契約を解除することとなります。
契約が解除された場合、永代使用権はなくなります。
したがいまして、永代使用権の存続を希望される場合は、墓地使用料をお支払いください。
なお、永代供養となっている方につきましては、請求書はお送りしておりません。
2.8.1.墓地使用料を支払っているのは少数にとどまるというのは本当でしょうか。
ほとんどの方から管理費をお支払いいただいています。
破産管財人に墓地使用料のお支払いがない場合、永代使用権を失うこととなりますので、ご注意ください。
2.9.墓地の使用者の名義を変更するにはどのようにすればいいでしょうか。
次の書類をダウンロードの上、必要事項を記入して破産管財人事務所まで郵送してください。
【使用者が生前に名義変更する場合】
【使用者が死亡した場合】
2.10.墓地使用者の住所や電話番号が変わりました。どのようにして届け出ればいいでしょうか。
次の書類をダウンロードの上、必要事項を記入して破産管財人事務所まで郵送してください。
3.分院の納骨堂について
3.1.分院の納骨堂はどうなるのでしょうか。
梅旧院は、別の法人に梅旧院分院の納骨堂の運営を委託していました。
しかし、墓埋法では、納骨堂を経営するためには、市町村長の許可が必要と定めています(同法10条1項、2条5項)。
梅旧院別院の納骨堂について許可を得ているのは、宗教法人である梅旧院です。
梅旧院の破産手続が終了すれば、許可が取り消される見込みです。
しかし、破産管財人としては、破産者の納骨堂経営の許可が取り消されたとしても、その後も納骨堂が維持されるよう努めて参りたいと考えております。
そのため、従来の法律関係を整理し、納骨堂の経営の許可を得ることができる法人に、納骨堂の事業を譲り渡すことを検討しています。
なお、厚生労働省の指針や大阪市の指針は、納骨堂の許可を受けることができるのは、宗教法人又は公益法人等に限ると定めています。
3.2.現在、梅旧院別院の納骨堂にお参りできるでしょうか。
梅旧院は、別の法人に梅旧院別院の納骨堂の運営を委託していました。
現在も、別の法人が納骨堂の運営を継続中しています。
したがいまして、納骨壇にお参りいただくことが可能です。
3.3.分院の納骨堂の契約者です。新たに遺骨を納骨することはできるでしょうか。
(1) 納骨の可否
納骨(収蔵)いただくことが可能です。
(2) 納骨手続書類の準備(埋葬許可証)
埋葬許可証が必要となりますので、ご準備ください。
多くの場合、骨壺の袋に火葬場の職員が入れてくれています。
お手元にない場合は、埋葬許可証を発行した市役所等で再発行を受ける必要があります。
(3) 納骨の手配
破産管財人から分院納骨堂の運営委託先に収蔵の手続を手配いたします。
contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、お名前と電話番号を必ず記載してください。
3.4.分院の納骨堂から他の納骨堂等に改葬することはできるでしょうか。
(1) 改葬の可否
改葬いただくことが可能です。
(2) 改葬手続書類の準備(受入証明書・納骨証明書・改葬許可申請書)
改葬先の納骨堂等から、受入証明書を取得してください。
受入証明書の提示を受け次第、破産管財人が納骨証明書を発行します。
これらの証明書やその他の必要書類とともに、改葬許可申請書に必要事項を記載し、浪速区役所に提出してください。
その際に必要となるその他の書類は、同区役所の2階21番窓口(住民情報(戸籍)) TEL 06-6647-9961)にご確認ください。
(3) 改葬の手配
破産管財人から分院納骨堂の運営委託先に遺骨の改葬の段取りを手配いたします。
contact@baikyu-in.jpまでご連絡ください。
その際、メールには、お名前と電話番号を必ず記載してください。
4.お問い合わせ
4.1.質問がありますが、どこに問い合わせればよいでしょうか。
contact@baikyu-in.jpに質問事項をお送りください。
個別の回答はいたしかねますが、よくある質問に対する回答をまとめてこのサイトでお答えする予定です。